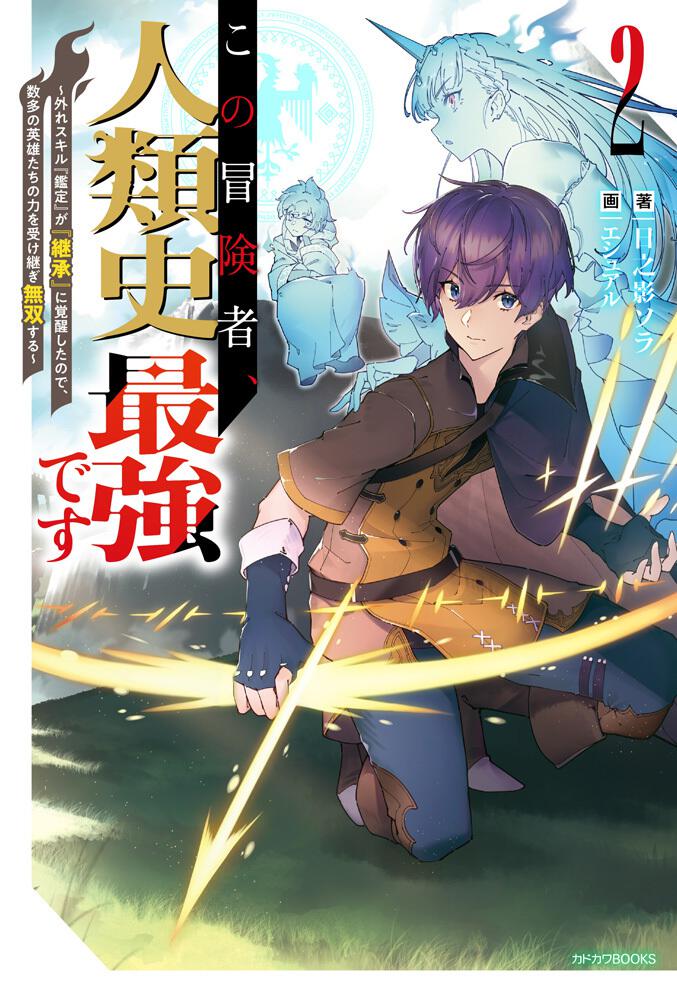8.個性『絆』
穢れの騒動から一夜明けた朝。
私とユーリは教会街で一番大きな図書館を訪れていた。
案内してくれている職員さんが立ち止まる。
「ここが聖女様について書かれた本の棚です。うちは王都の大図書館よりも古いですからね。数はありませんが、それなりに古い本もありますよ」
「ありがとうございます。探してみます」
「いえいえ。では何かあったら呼んでください。私は受付にいますので」
「はい」
「案内ありがとうございました」
ユーリが深くお礼をして、私も一呼吸遅れて頭を下げる。
職員さんが見えなくなるまで見送ってから、私たちは揃って本棚へ身体を向けた。
ユーリが腰に手を当てて言う。
「さてと、探すか」
「うん」
私たちは本を手に取り、中身をパラパラめくっていく。
探しているのは聖女について書かれた本。
その中でも、歴代聖女の個性について詳しく記されているもの。
くどいようだけど、聖女には個性がある。
当たり前のことだから、深く考える人は少ない。
ただ、私にはその個性がない。
と、つい昨日まで思い込んでいた。
だけど今は、違うと思っている。
あの時、私の中にある聖女の力が急激に強まって、あふれ出たようだった。
身体がすごく熱くなって、奥から何かが膨れ上がるような感覚。
「あんなの……今まで一度もなかったのに」
「才能が眠っていたのかもしれないな」
ユーリはそう言いながら、手に持っていた本を閉じて棚に戻す。
「もしくは条件があるのか……どっちにしろ、あんなことが出来るのに、無個性だなんてありえない」
「……うん」
ユーリがそう言ってくれたから、私は一つの心当たりに行きついた。
だから、おぼろげな記憶を頼りにこうして本を探している。
「なぁレナ。君が言っていた本って、どんな題名だったんだ?」
「えっと、確か聖女の日誌? みたいな名前だった気がするよ」
「随分曖昧だな。いつ読んだの?」
「どうだったかなぁ。大聖堂に入る前だったと思うよ。屋敷にあった本で一番古かったのは覚えてる」
探している本は、一度読んだことがある。
ペルル家の屋敷にある書棚にあった本。
その本の最後、数ページにだけ書かれていたのは――
「おっ! もしかしてこれじゃないか?」
「見つけたの?」
「たぶん」
ユーリが手に持っている本を見る。
黒背表紙と、横から見えるページは茶色く黄ばんでいて、古さが一目でわかるほどだ。
見覚えがある外観に喜び、両目を大きく見開く。
「それだと思う!」
「良かった。えっと、最後のほうのページなんだよな?」
「うん」
ユーリは本を左手に持ち、右手でページをめくる。
私は隣から覗き込むように眺めながら、懐かしい記憶をたどる。
自分が聖女であると知り浮かれ、無個性だと知って悲しみ、そんなはずはないと逃避した。
「あった」
だから、このページを読んで僅かに希望を持ったことを思い出す。
私とユーリは一緒に、ページの冒頭に書かれた言葉を口にする。
「「絆の聖女」」
今からずっと昔に存在したとされる聖女の一人。
絆という個性を持ち、特定の誰かと繋がり絆を深めることで真の力を発揮する。
弱い絆では力を十分には発揮できないとも、この本には書かれていた。
「レナが言っていた心当たりはこれか」
「うん。もしかしてなんだけど、私がそうなんじゃないかなって」
「絆……か」
穢れとの戦いを思い出す。
ユーリが私を守ろうとして傷つき倒れかけた。
それでも倒れず立ち上がり、彼は私を守るために剣を握った。
「あの時……ユーリが死んじゃうかもしれないと思って、悲しくて……思ったの。死んでほしくない。離れたくないって。そしたら力が溢れてきて」
「俺はただ、レナを守りたかった。ここで倒れたら君が死んでしまうかもしれない。だから倒れるわけにはいかないんだって、強く自分に言い聞かせたよ」
「うん……すごく伝わったよ。ユーリが本気で私を守ろうとしてくれてること」
傷つき、命だって危うい状況だった。
逃げ出したって文句は言わない。
そんな中、彼は臆することなく立ち向かい、私の前を譲らなかった。
嬉しかったし、格好良かった。
思い出すと、何だか恥ずかしくなってきて……
「俺が考えていたのは君のことで、同じように君も俺のことを心配してくれていたんだな。互いに互いを心配して、心から失いたくないと思った。だから絆の力――で……」
と、途中まで話して互いの顔を見つめる。
ユーリの頬がほんのり赤くなって、私の頬も徐々に熱くなる。
彼は無意識に言葉を紡いでいたらしい。
その意味を今さら理解して、恥ずかしくなって顔を背けた。
「か、確証はないけどね?」
「そ、そうだな」
恥ずかしくて、ユーリの顔が見れない。
ユーリも同じように顔を背けているだろう。
絆の聖女という言葉が頭に浮かんで、もしそうなら私たちは、あの時確かな絆で結ばれていたということになる。
そんな風に思ったらどんどん恥ずかしくなって、顔がポカポカ湯気が出そうになる。
するとユーリが、ぼそりと口にする。
「確証はない……けど、当たってるといいな」
「え?」
思わず顔を見た。
ユーリは思った通り横を向いていて、頬がさっきより赤い。
そのまま横を向きながら、ユーリは続ける。
「お互いを思いやる気持ちが力になったのなら、それってすごく良いことだろ?」
恥ずかしそうに、嬉しそうに。
ユーリの言葉に私の心臓は大きく鼓動を打つ。
「うん」
私も、そうであってほしいと思った。