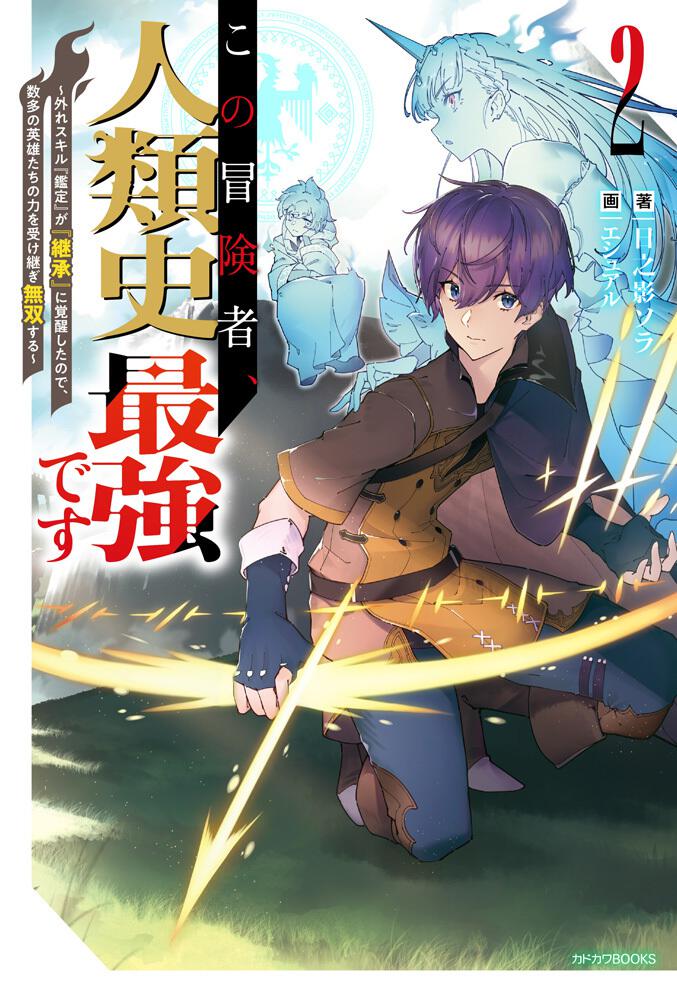38.憧れています
一年と少し前。
大聖堂に入った私は、周囲からの視線を気にして小さくなっていた。
ペルル家という名前だけで注目されるのに、個性のない聖女という肩書も相まって、私を見る目はとても冷ややかだった。
みんな私を見ながらヒソヒソと話す。
時折聞こえる笑い声が、全部私のことを笑っているんじゃないかとさえ感じた。
「嫌だな……」
そう呟いて大聖堂を出ようとした時、彼女は私に話しかけてきた。
「こんにちは、レナリタリーさん。私はセレイラです」
彼女は名乗ってくれたけど、名前を聞く前からよく知っていた。
十数年以来の天才。
光の個性を持つ聖女セレイラ。
その名前は大聖堂に入った時点で広まっていて、私とは違う意味で有名人だったから。
「お互い立派な聖女になれるよう、これから一緒に頑張りましょうね」
「は、はい」
話したのはたったのそれだけ。
大した会話じゃない。
彼女自身、ただの挨拶のつもりだったのだろう。
私だけじゃなくて、他の人にも同様に挨拶をして回っていたから。
それでも私は嬉しかった。
誰もが遠目に見て笑う中で、ちゃんと声をかけてくれたのは、彼女が初めてだったから。
それからずっと彼女を見てきた。
私とは全く違う道を行き、常に最前列を歩く彼女を。
憧れたし、凄いと思った。
天才と呼ばれた彼女は、いつだって自分を強く見せるために努力していた。
ひょっとしたらみんなは知らないのかもしれない。
大聖堂に入ったばかりの頃、彼女はみんながいなくなってからも、一人で力の訓練をしていたんだ。
私はそれを見ていた。
見て、真似した。
いつしか彼女は、私の目標になった。
どれだけ距離が離れても、哀れまれようとも。
私は彼女のことを、嫌いにはなれない。
◇◇◇
「だ、大丈夫ですか? セレイラさん!」
「レナリタリーさん……」
ギリギリの所で間に合った。
二人とも早すぎて置いていかれた時はすごく焦った。
さすが光の個性。
ガリウスさんのお陰でセレイラさんは無事だ。
「ガリウスさんは!」
「心配ありません。傷は酷いですが意識はあります」
「良かったぁ」
「それより貴女です! ドラゴンの前に出てくるなんて馬鹿ですか!」
私は結界でドラゴンの攻撃を凌いでいた。
セレイラさんみたいに街を覆うほどの結界は作れないけど、自分たちを囲む程度の結界なら作れるようになった。
お陰で二人を守ることが出来ている。
とはいえドラゴンの攻撃はすさまじく、気を抜けば一瞬でもっていかれそうだ。
セレイラさんの言う通り、こんな恐ろしい相手の前に出てくるなんて、私は馬鹿なのかもしれない。
だけど……
「大……丈夫です! 私にも……頼れる騎士がいますから!」
「おおお!」
地面を蹴り上げ高々と跳びあがり、ユーリはドラゴンの頭上に剣を振るう。
衝撃を受けてドラゴンが怯み、破壊の炎が止む。
ユーリがドラゴンの前に降り立ったことで、私たちに向けられていた敵意は彼に移行した。
「レナ! 結界に全力を注いでくれ! こいつ相手に守りながらじゃ不利だ!」
「わかった! 信じているからね!」
「おう! 俺も信じてる」
ユーリは振り返らず、剣を構えてドラゴンと対峙する。
信じている。
その一言さえあれば私たちは大丈夫。
「セレイラさんはガリウスさんの治療をお願いします。ここは私が守りますから!」
「……わ、わかったわ」
さすがのセレイラさんも、この状況では文句も言えない。
ガリウスさんの怪我はひどく危険な状態で、今のセレイラさんに治療と結界を同時に行う余力はない。
他人に自分の身を任せるしか出来ないなんて、彼女にとっては屈辱だろう。
と、私が勝手に思い込んでいたら……
「どうして助けたの?」
「え?」
「私は……貴女のことを見下していたわ。酷いことも……何度も言った。助ける理由なんてないはずよ」
「……」
彼女の声は震えていた。
弱気になっているセレイラさんを見るのは初めてだ。
きっと、他の誰も見たことがないだろう。
今だからこそ、私にだけ見せている。
私はしゃがみ込み、セレイラさんと目線を合わせる。
「私、セレイラさんにずっと憧れていたんです」
「え……?」
「セレイラさんって大聖堂に入ったばかりの頃、一人で遅くまで練習してましたよね?」
「なっ、貴女知ってたの?」
セレイラさんは恥ずかしそうに頬を赤らめる。
この表情も、普段の彼女が見せない顔の一つだ。
「のぞき見してしまってごめんなさい。でも、セレイラさんが頑張っている姿をみて、私も頑張らなきゃって思えました。あれがなかったきっと……私は途中で逃げ出していたと思います」
「……それでも、私が貴女に言ったことは変わらないわ」
「そうですね。でもそれだって、自分を追い込むためだったはずです。セレイラさんは頑張り過ぎなんです」
何でも一人で出来てしまえる。
それは間違いで、彼女は何でも一人でやれるように自分を追い込んでいた。
周りは彼女を天才と呼ぶけど、ただの天才じゃない。
努力して、追い込んで、完璧であろうとし続けた彼女を、私はただ尊敬する。
「私だって昔のままじゃないんです。少しずつだけど、ちゃんと前に進んでいます。だから……」
私は彼女の手を握る。
彼女の手は冷たくて、冷え切っていた。
それを温めるように優しく包み込む。
「私のことを少しだけ、ほんの少しだけでもいいので……信じてくれませんか?」
「レナリタリーさん……」
彼女は多くを背負い過ぎている。
その一つでもいいから、私にも分けてほしい。
昔の私には無理でも、今の私なら背負うことが出来るから。
彼女の身体が光り出す。
それは激しく、優しい光だった。