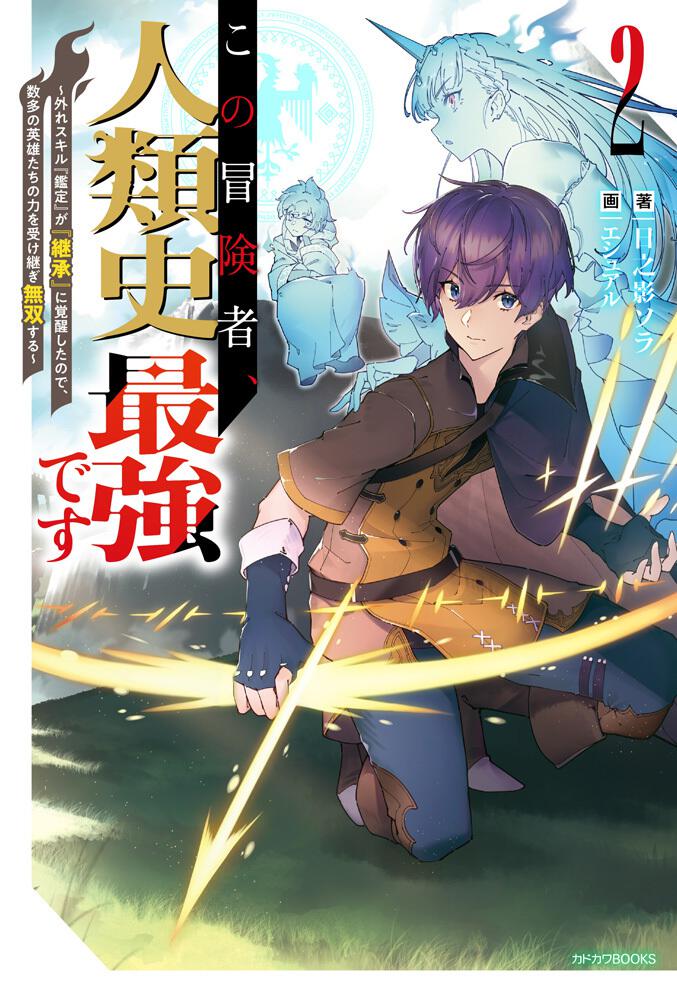33.同期との再会
世界の危機と大聖女様のお姿。
理解に時間のかかる出来事を終えて、私たちは一旦教会へ戻ることにした。
揺れる馬車の中で、私は結晶に閉ざされたミカエル様のことを思い返す。
「ミカエル様が……私と同じ絆の聖女だったなんて」
「お姉さまは生まれた瞬間から特別だったのですね! さすがラトラのお姉さまです」
「特別……」
その通りなのだろう。
絆の聖女は、この世界でたった二人だけ。
かつて世界を救い、今もなお守り続けている偉大な聖女様と、落ちこぼれで何もできなかった私。
同じと呼ぶにはおこがましいのだけど、事実だから仕方がない。
ただ……ミカエル様の今を見てしまうと、素直に喜べなかった。
結晶に閉ざされ眠り続ける彼女。
そして、その彼女と共に生き、戦い続けてきた騎士のアレスト様。
二人の間にある絆は、何千年経とうと続いている。
そんな二人の絆に、私たちが届くことが出来るのだろうか。
「ミカエル様のこと……もっと聞いておけばよかったなぁ」
「それはまた今度だ」
馬車を運転しているユーリが、背を向けたまま話す。
「参考にしたいとか考えているだろ?」
「ぅ、よくわかったね」
「わかるさ。でも必要ない。俺たちは俺たちなんだ。誰かを真似る必要なんてない。自分たちのペースで、進んでいけば良いんだよ
「……うん」
ユーリの見透かしたようなセリフに、不安で震えていた心が落ち着きを取り戻す。
彼の言う通りだ。
私たちは、私たちなりのペースで歩いていけば良い。
誰かの真似をしたって、それは私たちじゃないのだから。
何より、私の胸に抱くこの感情は、他の誰でもない私だけの気持ちだから。
やるべきことが増えただけで、やりたいことは変わらない。
◇◇◇
一度教会へ戻った私たちは、簡単に街の人たちに事情を説明した。
これから不規則的に街を離れる機会が増えること。
私たちがいない間は、王都から医療者が派遣されること。
聖女として大切な役割を果たしに行くのだと伝えたら、驚くほど簡単に納得してくれた。
「聖女様は素晴らしいお方だ。それなのにワシらが独占するわけにはいかん」
「そうそう。ちゃんと帰ってきてくださるなら安心だしなぁ」
街のみんなは優しくて、信頼してくれている。
それが言葉や表情の節々から感じ取れて、思わずほっこりしてしまった。
言ってしまえば赤の他人。
関りはあっても深くはない間柄で、こんなにも信頼してもられるなんて、幸せ以外の何物でもない。
私にとっても、みんなにとっても。
この街が帰る場所になってくれて、本当に嬉しく思う。
それから三日ほど過ごし、私たちは街を出た。
向かった先は王都からも近い大きな街。
国内で三本の指に入るほど栄えているウエストという街だ。
担当している聖女は――
「『光』の聖女セレイラ・レルネティア。お姉さまと同期で派遣された聖女さまですね」
ラトラは自分で調べまとめた資料に目を通している。
私はそれを隣で読みながら、ユーリは馬車を運転している最中だ。
「大聖堂卒業後すぐに三大都市に派遣。十数年以来の天才……ですか」
「セレイラさんは凄い人だよ。大聖堂に入ってすぐに主席に選ばれたし、その後もずっと成績はトップだったよ」
「そのようですね。ただ、自分の才能にうぬぼれて、他の聖女のことを見下している傾向があるようですが」
「そ、そんなことまで調べたの?」
ラトラの資料にはびっしりと彼女の性格まで書いてあった。
中には私が知らないようなことまで。
どうやって調べたのか知らないけど、ラトラの将来がちょっぴり怖い。
複雑な感情を抱く私に、運転中のユーリが話しかけてくる。
「同期ってことは話くらいはしたことあるのか?」
「う、うん……一応。よく話しかけられてたよ」
内容はお察しの通り。
成績トップの彼女からしたら、成績最下位の私なんて石ころみたいなものだっただろう。
いつも笑われて、馬鹿にされていた。
正直に言えば、あまり会いたくはない人だ。
「プライドが高く傲慢……それで聖女を名乗っているなんて馬鹿らしいです。少しはお姉さまを見習ってほしいものですね」
「あははは……で、でもセレイラさんが救援要請なんてするとは思わなかったよ」
プライドの高さはずっと感じて来た。
誰かに頼るなんてしない。
全部自分で何とか出来るから、騎士だって必要ないとさえ口にしていたこともあった。
そんな彼女が救援要請……よほどのピンチなのだろう。
◇◇◇
王都よりは短い馬車の旅を終え、私たちは王国三大都市の一つウエストに到着した。
街並みは王都に酷似している。
規模を少し小さくしただけで、外観的特徴に大きな差はない。
道行く人の賑わいも、王都で見て来たそれに近い。
馬車を預けてから、セレイラさんがいる教会に向う。
今はちょうどお昼時で、休憩している頃だろうとラトラが教えてくれた。
街の人の人数からして、解放時の教会はさぞ混雑していることだろう。
休憩が終わってしまう前に挨拶を済ませようと、私たちは気持ち駆け足で街を進む。
私たちは教会にたどり着く。
「立派な教会だね。私たちの教会よりずっと大きい」
「大事なのは大きさじゃないだろ?」
「大事なのは見た目ではなく中身ですよお姉さま!」
「それはわかってるけど」
少しは羨ましいと思ってしまう。
私は深呼吸をしてから、教会の扉を開ける。
「こんにちは。救援に――は?」
セレイラさんは私と目を合わせる。
疑問と苛立ちを混ぜ合わせた表情に、私は昔を思い出した。