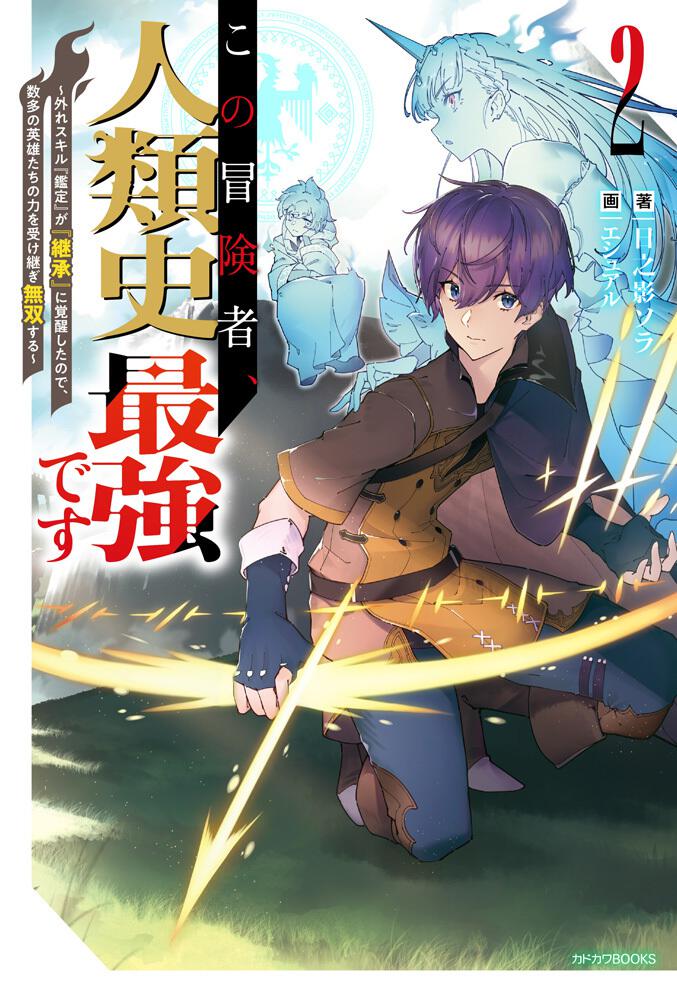29.大聖女ミカエル
大聖女ミカエル様。
司る個性は『守護』。
王国に属する聖女の中でもっとも強い力を持つ聖女様で、王都の結界を一人で維持している。
そのため王都から出ることは出来ないらしく、またほとんどの人が顔を知らない。
知っているのは、大聖堂に飾られていた絵だけ。
綺麗な金色の髪に白い肌の、すごく綺麗な女の人だった。
「それじゃ、僕は先に王都に戻るからね」
そう言ってアレスト様は教会の扉を開ける。
身体が半分くらい外に出た所で顔を後ろに向け、私たちに言う。
「王都についたら大聖堂にきてくれると助かるよ」
「わかりました」
「うん。それじゃっ」
私が返事をすると、アレスト様は軽く手を振って姿を消した。
いなくなって扉だけがパタンと閉まる。
出て行ったのではなく、いなくなったことに私は驚く。
「え、消えた?」
「転移だよ。アレスト様は大聖女様の他にも契約しているから、そのお力だと思う」
「そ、そうなんだ……」
アレスト様がいなくなって、私は大きくため息をこぼす。
緊張が一気に解れたのだろう。
足や肩の力も抜けて、少しだけ姿勢が丸くなる。
「大丈夫?」
「う、うん。ちょっと緊張過ぎたかな」
「俺もだよ。まさかアレスト様がいらっしゃるなんて思いもしなかったから。それに比べてラトラは毅然としてて凄いな」
「ふふっ、ラトラがお相手するのは普段から目上の方でしたからね」
ラトラはニコリと笑いながら言う。
ペルル家の令嬢として恥ずかしくないよう、私よりも厳しく育てられていたから。
「それでどうしますか? 特に期日はおっしゃっていませんでしたけど」
「今から出発したほうが良さそうかな? 街の人たちには俺が伝えて回るから」
「うん。私とラトラで出来る準備はするね」
「お願いするよ」
それから私たちは手分けして、王都出発の準備を始めた。
馬車の手配と街の人への説明をユーリがしてくれて、私たちは長旅の荷物を整理する。
ここは辺境の街だから、王都へ行くのも時間がかかる。
衣類に食料はもちろん、緊急時に備えて野宿できる準備もしておく必要があった。
約二時間かけて準備と説明を終え、私たちはユーリが運転する馬車に乗って王都を目指す。
ガタガタと凸凹な地面を走る振動に揺られながら、小さくなっていく街を馬車の窓から見つめる。
元々聖女がいなかった街だし、最近は病気やけがをする人も落ち着いてきたから、大丈夫だとは思いつつも……
「心配ですか? お姉さま」
「うん。でも……」
正直に言えば、王都のことも気になってはいる。
聖女の憧れとも呼べるミカエル様にお会いできる機会なんて、普通はありえない。
大聖堂に飾ってあった絵を思い浮かべながら、どんな方なのだろうと想像を膨らませていた。
それに、不思議と不安はなかった。
王都ではあまりいい思い出はなかったのに、嫌な気分でもない。
きっとそれは、一緒にいてくれる二人がいるから。
◇◇◇
馬車に揺られ数日。
私たちは王都へと帰還した。
王都を離れてからそれほど長い時間は経っていない。
それでも……
「懐かしい」
そう思うのは、私がここで生まれ育ったからだ。
どれだけ嫌な思い出が多くても、悪いことばかり続いても、生まれた場所は懐かしく思うと知った。
門をくぐって感慨に耽っていると、馬車を業者に預けて来たユーリが駆け足で戻ってきた。
「おまたせ。それじゃ大聖堂へ行こうか? それともどこか寄ってからにする?」
「ううん、大聖堂でいいよ」
「わかった。ラトラもそれいいか?」
「はい。ラトラはお二人に任せます」
三人とも大聖堂に向うことで了承し、まっすぐ目的地へ向けて歩き出す。
王都の賑わいは相変わらずで、商店街は多くの人でごった返していた。
私たちは波に飲まれないようわき道にそれて、少し大回りしながら大聖堂を目指した。
道中、知り合いに会わないかなと思って身構えていたけど杞憂に終わる。
同期はみんな各地に派遣されたし、王都に残っている知り合いのほうが少ないか。
強いて言えば彼……元婚約者のアウグスト様くらいだけど。
「出来れば会いたくないなぁ」
と小さくぼやく。
周囲の音が大きくて、二人には聞こえていなかった。
そのまま寄り道せず、私たちは大聖堂に到着する。
「ここはもっと懐かしい」
「ああ」
大聖堂はユーリにとっても馴染みのある場所。
同じ敷地内に騎士の養成所もあるから、何度も目にする機会はあったと思う。
そして私たちは、この土地で出会った。
あの出会いがあったからこそ今がある。
そう思うと、無性にお礼が言いたくなって、私たちは顔を見合わせる。
言いたいことは、きっと同じ。
「中に入ろうか」
「うん」
だから敢えて口にしない。
私たちは大聖堂の中へと足を踏み入れる。
すると、記憶に新しい声が私たちを呼び止める。
「待ってたよ。三人とも」
「「アレスト様」」
「長旅ご苦労だったね。さっそくだけど付いてきてもらえるかな」
私たちはこくりと頷く。
その後、アレスト様に案内されて大聖堂の奥に向った。
案内してもらったのは、これまで立ち入り禁止になっていた部屋。
厳重に鍵をかけられ、許可がなくては立ち入れない。
そこに私たちは踏み込む。
アレスト様を先頭に扉を開けると、地下に通じる階段があった。
白い炎が燃えるランタンが壁に付いている。
不気味ではないが怖い雰囲気だ。
私たちは階段を下る。
その道中、アレスト様が質問を投げかけてくる。
「聖女レナリタリ―は彼女、ミカエルのことをどれくらい知ってる?」
「えっと、『守護』の聖女様で、王都を守る結界を維持してくださっていると」
「うんうん、まぁそうだね。あとは守護の聖女は親から子に受け継がれるもので、代々王族の家系の者がなる。騎士である僕も同様に、親から子へ名を受け継ぐ、かな?」
「はい」
アレスト様が口にした内容は、見習い期間に教えてもらった知識だ。
逆にそれ以上のことは知らない。
話をしていると階段が終わり、古びた鉄製の扉が目の前にある。
「この先に彼女はいる。今から見るもの、聞くこと全て他言無用だよ」
「はい」
私はごくりと息を飲む。
そして、扉が開いた瞬間に呼吸を忘れてしまった。
大聖女様の外見は絵で見た通りだった。
黄金の白い肌の美しい女性。
ただし、氷のような結晶に閉じ込められ、目を閉じていた。