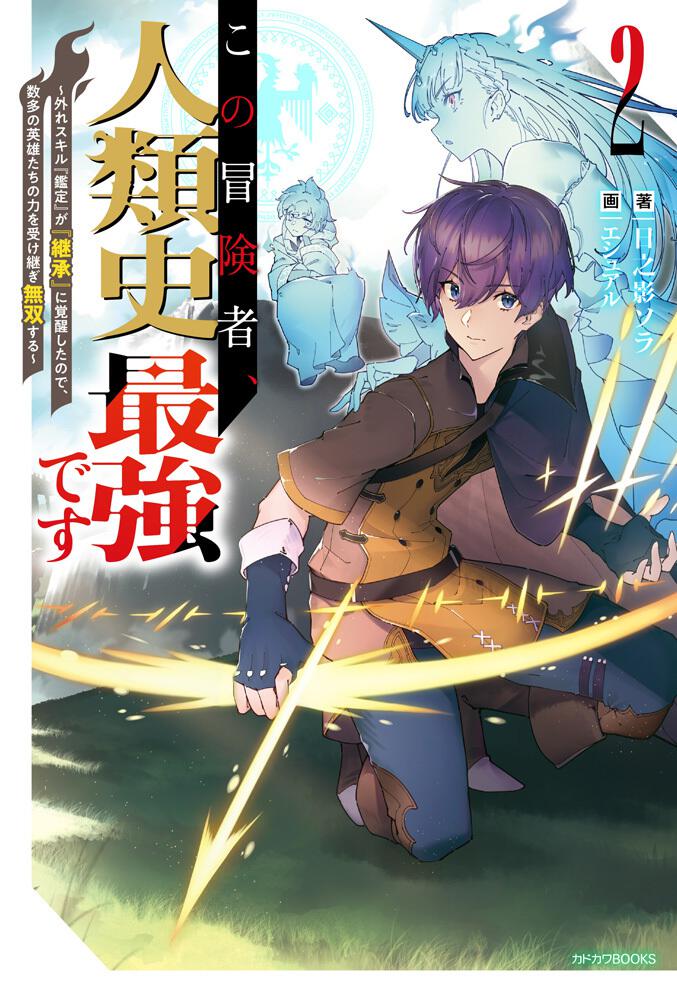27.王国最強の騎士
「おはようございますお姉さま!」
「おはよう、ラトラ」
「お身体の調子はいかがですか? どこもおかしなところはありませんか?」
「だ、大丈夫よ。心配してくれてありがとう」
朝になった途端にラトラが私の部屋を訪ねてきた。
勢いよく扉が開いた時には驚いたけど、ラトラが私を見て半泣きになった時はもっと驚いた。
それだけ心配してくれていたということだろう。
私の身体を隅から隅までペタペタ触り、無事を確認するのはちょっと恥ずかしかったけど。
「ユーリから聞いたよ。私のために頑張ってくれたって。本当にありがとう」
「そんな、ラトラはお姉さまの妹として当然のことをしただけです。それに……これまでのことを考えたら、これくらいじゃ足りないくらいです」
ラトラはそう言って申し訳なさそうに顔を伏せる。
これまでのこと、それはきっと素直になれなかった日々を指しているに違いない。
仲直りしてからも彼女は悔いている。
「ありがとうラトラ。ラトラは自慢の妹だよ」
「お姉さま……はい!」
私が頭を優しく撫でると、ラトラは嬉しそうな笑顔を見せてくれた。
こうしていると、何だか昔に戻ったみたいで落ち着く。
そんな折、しまった扉の向こう側から私たちを呼ぶ声が聞こえてくる。
「レナ、ラトラ」
「ユーリ」
「お兄さま!」
彼はガチャリと扉を開け、部屋の中へ入ってくる。
「おはよう二人とも。朝食の準備が出来たけど来れる?」
「うん」
「はい!」
◇◇◇
三人で朝食をとる。
穏やかな時間を過ごしながら、私は二人に尋ねる。
「あの後はどうなったの?」
「特に何ともなってないよ。領主のことが心配なら気にしなくて良い。彼はもう何もできない。ラトラのお陰でね」
「はい! もしまた不正を働くようなら容赦はしません!」
「そ、そうなんだ……」
ラトラが領主の悪行を暴き出して、彼を脅していたことは覚えている。
その後の反応はうろ覚えだけど、二人の反応を見る限り大丈夫だったのだろう。
そういえば……
「彼って誰だったのかな」
「何の話だ?」
ユーリが反応する。
このことはまだ二人に話していなかった。
私は領主の発言を思い出しながら説明する。
「領主者様に私のことを教えた人がいるみたいなの」
「レナのことを? 一体何のために?」
「わからない……ラトラは心当たりとかある?」
「いえ、ラトラも初耳です。領主のことは隅々まで調べたはずですが……」
ラトラの調査網にも引っかからなかった彼と呼ばれる人物。
何となく嫌な感じはする。
というのも、ラトラに穢れの力を与えた人物と同じなんじゃないか。
そう思ってラトラに聞いてみた。
すると彼女はしばらく考えてから答える。
「まだわかりません。ラトラが覚えているのは男性の声だったということだけなので」
「でも十分に可能性はありそうだね。君を、聖女を狙ったなら」
「うん……」
とても嫌な感じだ。
私たちの見えない所で、良くないものが広がっている気がする。
漠然とした不安が徐々に肉付けされて、いずれ形を成すような予感。
「まぁといっても、今は俺たちに出来ることをしよう。今日もしっかり働いてもらうよ、聖女様」
「わかってるよ」
ユーリの言う通り。
悩むのは後にして、私は聖女としての務めを今日も果たそう。
食事を終えた私たちは、教会で人を迎える準備に取り掛かる。
簡単にお掃除をして、私も聖女らしい格好に着替え終わった。
すると、トントントンと戸を叩く音が聞こえる。
「ん? もう来客か」
「随分と早いですね」
ユーリとラトラが一緒に時計を見る。
教会を開ける時間には少し早い。
「レナ、どうする?」
「私は大丈夫だよ。準備は終わってるし」
「わかった。どうぞお入りください」
ユーリが扉に向って大きめの声で呼びかける。
私は普段通り聖女らしく、にこやかな表情で待った。
静寂が数秒続く。
「あれ? どうぞお入りください!」
ユーリがもう一度呼びかけた。
しかし返事はない。
まさか帰ってしまったのだろうか?
ノックから数秒しか経過していないのに、それは考えにくい。
「ちょっと見てくるよ」
「うん」
ユーリが一歩踏み出す。
その瞬間、聞きなれない声が私たちの耳に吹き抜ける。
「その必要はないよ。僕はもう中に入っているからね」
「え?」
「なっ……」
私たちは振り返り、驚愕する。
中に入っていたことをではなく、その人物に。
「こんにちは。いや、おはようかな? 聖女レナリタリー、騎士ユーリ、ペルル家のラトラお嬢様」
「あ、貴方は……どうして貴方がここに」
ラトラが驚きを声に漏らす。
私とユーリも同じことを考えているはずだ。
銀色の髪に特徴のある怪しげな仮面。
腰に携えた剣には、王国の紋章が刻まれている。
黒い騎士の服装も、彼だけに許された特注品。
王都に暮らす者であれば、彼のことを知らないわけがない。
王都を守護する大聖女ミカエル様。
その騎士にして、王国最強最高の剣士――
「剣帝……」
「アレスト様?」
ユーリと私で彼の名前を口に出す。
剣士にとっての頂であり、聖女にとっても憧れを抱く存在。
遠い雲の上にいるはずの人が、私たちの目の前に立っていた。
その仮面の内側は、果たして笑っているのか、呆れているのか。