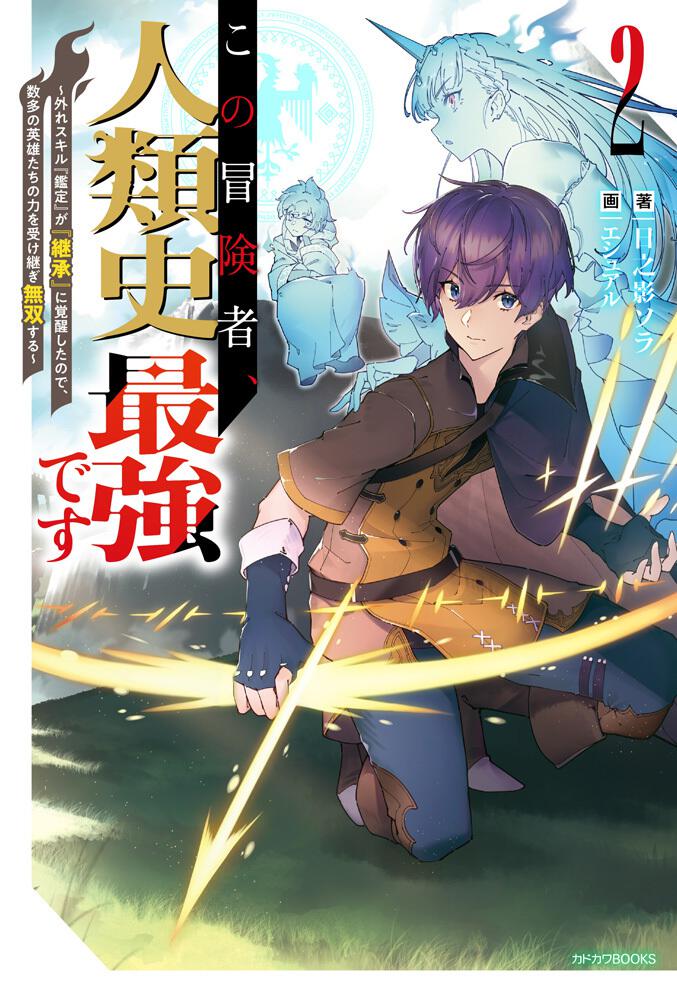23.領主との対面
「お兄さま! ラトラも何かお手伝いします!」
「そう言われてもなぁ~ というか何で俺に聞くんだ?」
「だってお姉さまのお仕事は聖女のお仕事でしょう? どれだけ望んでも、聖女の代わりはできませんから。だからお兄さまに聞いているんです」
「なるほど。うーん……」
ユーリは難しい表情をして考えだす。
視線はラトラに向けたまま。
「ありません……か?」
「いや別にないわけじゃないんだが~ そっちじゃなくて、そのお兄さん呼びはむず痒いなと思って」
「そうですか? ですが時間の問題だと思いますけど……あ!」
突然、ラトラが大きな声を出した。
私とユーリは驚いて、身体をビクッと震わせる。
「ど、どうしたの? ラトラ」
「忘れるところでした! ラトラがここへ来た理由は、お姉さまにお伝えしなければならないことがあったからなんです」
「私に?」
「はい。お姉さまの婚約者のことです」
「婚約者?」
アウグスト様のこと?
いやでも、アウグスト様はもう婚約者じゃないし……
「そのご様子だと、まだ伝わっていないのですね」
「何のこと? アウグスト様に何かあったの?」
「いいえ、違います。実は先日――」
ガラガラ、ガシャン。
外から聞こえた音に全員が反応する。
ラトラも話の途中で口を瞑り、窓の外を見る。
どうやら馬車が停まっているらしい。
それも豪勢な、貴族が乗っているような見た目をしていた。
ユーリがラトラに尋ねる。
「ラトラの馬車……んじゃないよな?」
「あれはおそらく、この地の領主の馬車です」
「領主の」
「はい。これはもう、ラトラからお話しする必要はなさそうですね」
そう言ってラトラは目を伏せる。
私たちには、彼女が言っている意味がわからなかった。
そしてわからないまま、教会の扉が開く。
ノックもなく、不作法に。
姿を見せたのは、髭を生やした小太りの中年男性だった。
服装は小綺麗でやけにキラキラした装飾が多い。
いかにも貴族のお金持ち、という風貌をしている。
「失礼する。この地に聖女が来たという話を聞いたのだが」
話ながら、私に視線を合わせて止める。
ニヤっとした笑顔が気持ち悪くて、背筋がぞっとする。
「ほうほう、聞いていた通り美しいではないか」
「あ、あの……私はこの街の聖女レナリタリーです。失礼ですが貴方は?」
「おっとこちらこそ失礼。私はこの地を治める領主、エルダーブ家当主のゴドウィンである」
ラトラがぼそりと口にした通り、馬車は領主のものだったようだ。
「いや実に美しいなぁ、気に入ったよ。さっそく私の屋敷まで来てもらおうか」
「え? 屋敷?」
何の話?
「何だ? 聞いてはいないのか?」
「な、何のことでしょう?」
「……ふむ、本当に知らないのか。この地に来た聖女は、我がエルダーブ家へ招き入れる仕来りがあるのだ」
「え、それって……」
嫌な想像が頭に浮かぶ。
領主のにやついた表情が、不安を加速させて。
「喜ぶが良い。君は私の妻になるんだ」
途中から予想は出来ていたけど、直接言葉で言われると、どっと来るものがある。
そして同時に理解する。
ラトラが伝えたいと言っていたのは、まさしくこのことだと。
婚約者のこと。
つまり、婚約者となり得る人物がいることを、彼女は伝えようとしてくれた。
私はごくりと息を飲む。
「そ、その……私は聖女ですので、この地を離れるわけには」
「それについては深く考えなくとも良い。君の地位や生活は、私が保証しよう」
「そういうことではなく」
「何だね? 不服なのか?」
領主は不機嫌な顔を見せる。
それでも、言わなきゃいけない。
言うべきことを。
勇気を振り絞って、私は声に出す。
「申し訳ありません。とても魅力的なご提案ですが、お断りさせていただきます」
「……聞き間違いかな?」
「いいえ、お断りすると申し上げました」
ちゃんと言えた。
威圧的な視線が怖くて身体を震わせながら、心の中ではホッとする。
でも、もし食い下がってきたらどうしよう。
その時は、ユーリやラトラも味方をしてくれるかな?
だったら心強いな。
「……そうか。それは悲しいな。しかしどうだ? 答えを出すには少々早計だとは思わないかね?」
予想していた反応と違う。
怒られるか、引き下がるかのどちらかだと思っていた。
そのどちらでもなく、彼は諭すように続ける。
「そんな簡単に判断せず、一度しっかり話をしないかね? そうだな、せっかくだし我が屋敷に招待しよう。そこでゆっくり話し合おうじゃないか」
「い、いえそれは――」
「良いではないか。高々一日程度、この地を留守にするだけだ。私も聖女とはいかような者なのか、知りたいと思っていてね? ぜひ色々と教えてほしい。話をして、それでも断るというならば仕方がない」
思った以上にグイグイ来る。
出来れば行きたくない。
でも、断っているのに押され気味で……私は助けを求めるようにユーリへ視線を向ける。
「お待ちください領主様」
「ん? 何だね君は?」
「お話に割り込んでしまい申し訳ありません。私は聖女レナリタリーの専属騎士、ユーリと申します」
「ほう、君が彼女の騎士なのか。で、何かね?」
「聖女は本来、配属された地から移動することはできません。それは規定に反します」
ユーリの言う規定とは、王国が定めた法律のこと。
聖女はその地を守護する者であり、やむを得ない理由がない場合、配属された地から離れてはならないとされている。
これに違反する、または違反を唆す行為は厳しく処罰される。
「……そうか。ならこうしよう! この街に私の屋敷があるのだ。そこで話そう。もちろん二人でな」
二人で?
ユーリやラトラは?
「騎士ユーリ、君は教会で待機していなさい。同じ街の中であれば、彼女と話すことは問題はないだろう?」
「それは構いませんが、私は彼女の騎士です。彼女を守るためにお傍に」
「その心配も不要だ。専属の護衛は私にもいる。それより君は、教会を無人にして良いと思っているのか?」
「それは……」
領主は鋭い眼光でユーリを睨む。
ユーリも領主相手に強く出れず、口を紡いでしまう。
それでも私は、一緒に来てほしいと思っていた。
「わかりました。本日中にお戻りいただけるのであれば」
「それは彼女次第だ。では行こうか」
「え、あの……ユーリ」
「……お帰りをお待ちしております。聖女様」
そう言ってユーリは頭を下げる。
仕方ないのかもしれない。
でも、私がほしかったのはその言葉じゃなくて……