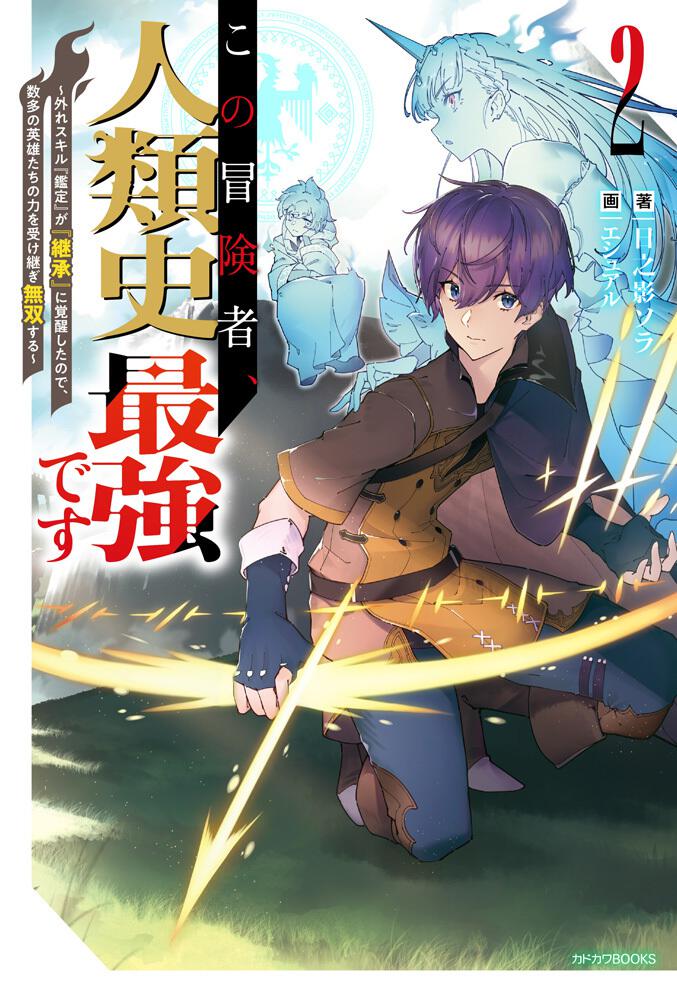20.信じたい
化け物が現れた場所に急行した。
その場所は、街の入り口。
「なっ……」
「これは……」
まっすぐ伸びる街道を塞ぐように、巨大な塊がそこにはあった。
塊、と表現する以外ない。
もはや生物の形はしていない異形の穢れ。
仮に例えるなら、猛毒に意思が宿り蠢いているように見える。
紫色の半液体が触手のようにウネウネ動き、本体らしき球体が中央にある。
「やっと来たかよ!」
「レナちゃん! 騎士君早く!」
アリサさんたちが穢れと戦い食い止めてくれている。
聖女の力を持たない彼女たちでは、穢れを祓うことはできない。
触手を斬り裂き、何とか止めるので精一杯。
余裕のない表情で私たちの名前を叫んだ。
「ユーリ!」
「ああ!」
ユーリが剣を抜き、穢れに突っ込む。
「皆さんは避難を優先して下さい!」
「わかりました。後は頼みます!」
ロイドさんが二人に指示を出し、街の中へ戻っていく。
彼らのお陰で被害は少ない。
入り口にあった小さな門は破壊されてしまったし、道もボコボコになっているけど、幸いけが人はまだ出ていない様子だ。
ユーリが触手を斬りながら私に言う。
「レナ! 一気に叩くぞ!」
「うん!」
私は目を瞑り、手を組んで祈りを捧げる。
ユーリに私の力を。
その片隅でふと、私はラトラのことを思い浮かべた。
入り口に走る途中、彼女の馬車はどこにもなかったから。
もう出てしまったのだろうか、と。
助けて――
「今の声……」
助けて――
怖いよ……痛いよ。
「ラトラ?」
聞き間違いじゃない。
ラトラの声が聞こえて来た。
それも酷く苦しんでいる声だ。
「どこ? ラトラ! どこにいるの!」
お姉――様……
私のことを呼んでいる。
弱々しい声だけど、ハッキリと聞こえた。
声の方向は――
「まさか……穢れの」
穢れの中心に目を凝らす。
聖女である私の眼は、穢れの本質を覗き込むことが出来る。
その眼に映ったのは、穢れに取り込まれたラトラの姿だった。
衝撃に眼を見開く。
その拍子に気付いたが、道の端に馬車が倒れていた。
街の人たちからしたら見慣れない、けど私には見知った馬車が。
「ユーリ! その穢れはラトラだよ!」
「なっ、は?」
「よく見て! 穢れの中心!」
ユーリは一時的に距離をとる。
彼もまた、目を凝らせば見えるはずだ。
私と同じように。
「う、嘘だろ」
「見えたでしょ! ラトラが穢れに取り込まれてるんだ!」
「っ、どうすればいい? このまま斬っても良いのか?」
「だ、駄目だよ! ラトラまで傷つけちゃ!」
穢れは問答無用にユーリへ襲い掛かる。
ユーリは攻撃を躊躇して、大きく跳び避ける。
「周りの触手は斬っても良いよ! でも中心は駄目!」
「それで倒せるのか? さっきから斬ってるけど全然効いてる気配ないぞ!」
「そ、それは……」
おそらく倒せない。
穢れに取り込まれたか、穢れを生んだのか。
どちらにしても、中心にいるラトラが依代になってしまっているらしい。
穢れを祓うなら、ラトラのいる中心部分を攻撃しなければならない。
ただその場合、間違いなくラトラも……
「何か方法はないのか!? このままだと押し切られ――っ」
「ユーリ!」
「大丈夫! まだ大丈夫だ」
まだ、という言葉が頭に響く。
ユーリはラトラを傷つけないよう消極的に戦っている。
守り優先の立ち回りは、私から見ても明らかだった。
彼の言う通り、このままだと押し切られる。
ラトラを傷つけず、穢れだけを払う方法を考えないと。
「考えて……ううん、ある。一つだけ」
でもこの方法は……一歩間違えれば私も危ない。
それでも私は、ラトラを助けたい。
覚悟を決めよう。
「ごめんユーリ!」
「レナ?」
説明している時間はなかった。
だから私は、彼に精一杯の視線を送る。
そして穢れに向って駆けだす。
「お、おいレナ!」
焦り心配するユーリの顔を最後に、私は穢れに呑み込まれた。
違う、飛び込んだんだ。
「大……丈夫」
結界術。
聖女の力で壁を作り、穢れを寄せ付けない結界とする。
昔の私には出来なかったことだけど、今は何とか自分を守るくらいは出来る。
「ラトラ……待ってて」
後はまっすぐ突き進むだけ。
穢れを押しのけかき分けて、ラトラの元へ。
お姉さま――
「ラトラ!」
声が聞こえる。
さっきまでよりも近く。
それに何?
一緒になって、何かが……流れ込んでくる。
「これは……ラトラの記憶?」
脳裏に映し出されたのは、ラトラが幼い日の光景。
私と一緒に遊んでいる時の風景だった。
楽しそうに、嬉しそうに遊ぶ二人。
この時はまだ、仲睦まじい姉妹だった。
そう、ラトラも思ってくれていた。
お姉さまの役に立ちたい。
ラトラは聖女にはなれない……けど、お姉さまの妹として頑張らなきゃ。
幼い彼女はそう思って、勉学に励んでいた。
それ以外にも理由はある。
両親は私に期待し、同時に絶望してしまったから。
その分、妹であるラトラに期待を寄せていた。
ただそれも、最初からだったわけじゃない。
ラトラには聖女の力がなかったから、その時点で諦めかけていたのだ。
私の知らない所で、ラトラに聞こえるところで、両親は心無い言葉を口にしていた。
今回も外れだ。
せめてレナリタリーより賢ければな……
「そんなこと言われて……」
ここままじゃ、ラトラはお姉さまの元にいられない。
頑張らなきゃ……もっと、もっと!
その一心でラトラは努力を重ねた。
私が才能だと思っていたそれは、彼女の努力の成果だった。
そうして彼女は貴族令嬢として恥じない立派な女性に成長した。
両親も彼女を見直し、優遇するようになった。
次第に、私とラトラの距離は離れていく。
きっかけは一つ、私のためだったのだと、この時初めて知った。