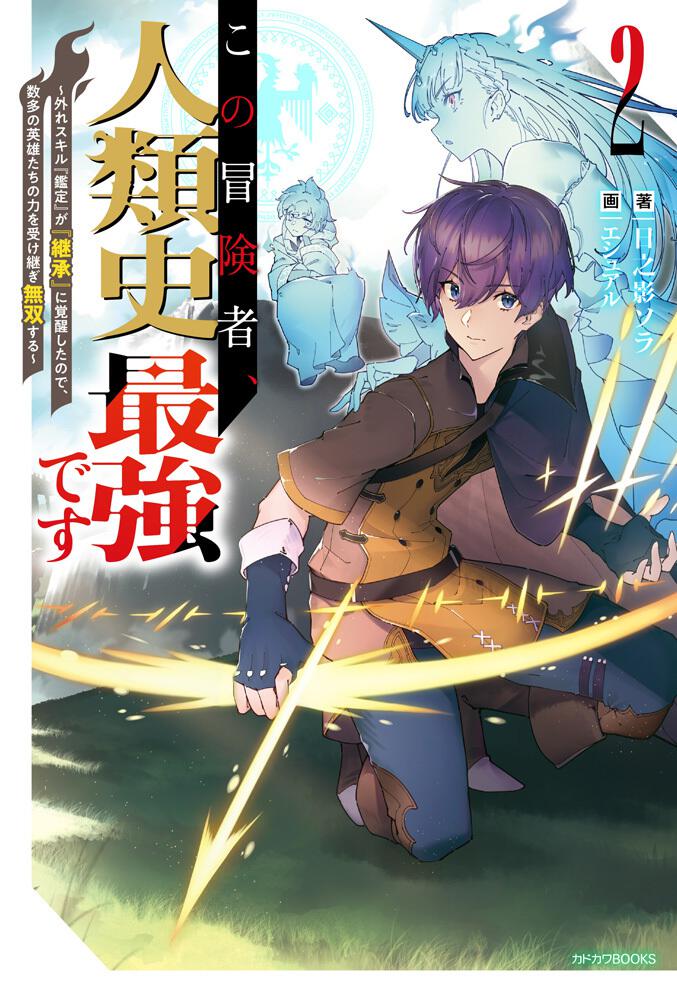16.予感
屋敷の庭には綺麗な花が植えられている。
温かくなると色とりどりの花を咲かせるその場所は、幼い私たちにとってお気に入りの場所だった。
「見てくださいお姉さま! お花で髪飾りを作ってみました!」
綺麗な花を編んで作った冠の髪飾りを、楽しそうな笑顔で私に見せて来た。
私の妹ラトラ。
この頃は六歳で、私は八歳だったと思う。
よく一緒に遊んでいて、この光景もその時のものだと理解した。
「すっごく綺麗ね! ラトラには物づくりの才能があるのかも」
「えっへへ~ これはお姉さまにあげます!」
「本当?」
「はい! お姉さまに似合うと思って作ったんです!」
そう言ってラトラは背伸びをして、私の頭に花冠を置こうとする。
身長差があって届かないけど、頑張って手を伸ばす。
そんな姿が愛らしくて、私は微笑ましさを感じながらかがむ。
「ほらやっぱり! 綺麗なお姉さまがもっと綺麗になりました!」
「ふふっ、ありがとうラトラ」
温かい風が吹き抜ける。
楽しかった思い出に、心が温かくなる。
そう、これは思い出だ。
懐かしい夢を見ていると自覚した時、私の意識が現実に引っ張れた。
「ぅ、う……朝?」
目を覚まして窓の外を見る。
清々しい晴天、とはいかなかった。
朝とわからないくらい薄暗く、雲がどんよりと空の青を隠している。
湿気なそこまで感じないから、雨は降っていない様子。
「良い夢だったのに……」
忘れかけていた夢。
せっかく懐かしくも楽しい夢を見て目覚めた朝がこれじゃ、あまり気分は良くない。
いや、良い夢ではあったけど、もう二度と訪れない光景でもある。
年齢のことじゃない。
私とラトラの関係は、あの頃から大きく変わってしまった。
「ラトラ……どうしてるかな?」
不意にそんなことを口にした。
こんな辺境じゃ、彼女がどうしているかなんて伝わらない。
あの子は頭も良くて優秀だから、アウグスト様とも仲良くやっていることだろう。
「もう関係ないか」
会うことはない。
向かい合うことはない。
話すことも、聞くこともないだろう。
これから私がこの街で聖女として生きていくように、彼女はペルル家の貴族令嬢として王都で生きていく。
私たちの道が交わることは……ないのだから。
だけど、何となく予感がしていた。
根拠も理由もないけど、どうして今さら夢を見たのか。
もしかすると、きっかけだったのかもしれない。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
「聖女様……私、妹と喧嘩しちゃったんです」
その日最後の訪問者は、小さく可愛い女の子だった。
彼女は泣きそうな顔で一人、この教会を訪ねて来た。
どうにも、些細なことで妹と喧嘩してしまったらしい。
多くはないけど、時折こういう相談事を持ち込まれることがある。
聖女の仕事は癒すだけじゃない。
時に迷える人々を導き、正すこともできなければ。
「お姉ちゃんなんて嫌いって言われて……あ、謝れば許してくれますか?」
「大丈夫です。ちゃんと謝れば仲直りできます」
「本当ですか?」
「もちろんです。だって二人は姉妹なのでしょう? ならきっと貴女の妹も、同じ気持ちでいるはずです」
自分の言葉に説得力を感じない。
「ありがとうございます! 私、妹に謝ってきます!」
「ええ、頑張って」
そんなこと、私が言う資格なんてないのに。
笑顔の裏で後ろめたさを感じながら、私は女の子を見送った。
扉が閉まって、肩の力が抜ける。
「どうかしたのか?」
「え?」
そんな私に、ユーリが後ろから声をかけて来た。
振り向くと彼は、少し心配そうな顔をしているように見えた。
彼は続けて言う。
「元気ないだろ? 何か嫌なことでもあったのかと思って」
「べ、別にそんなこと……ないよ」
尻つぼみになる声量。
ユーリは大きくため息をこぼす。
「どう見てもそんなことあるじゃないか」
「ぅ……」
「何があったんだ?」
ユーリは私のことを心配してくれていた。
相談しようかと、途中まで出かかる。
だけど、懐かしい夢を見て考えさせられている、なんて相談してもどうしようない。
彼を変に困らせたくない私は、出かけた言葉を飲み込んで答える。
「ううん、本当に大丈夫だから」
「本当か? 疲れてるなら休んでも良いんだぞ?」
「へーきだよ。それよりほら! そろそろ街を周らないと帰りが遅くなっちゃう」
「……」
ユーリは難しい顔をして黙り込む。
きっと彼にはわかっている。
私が誤魔化していることなんて。
「……わかった。準備するよ」
そう言った彼はちょっぴり呆れたように微笑む。
気を遣って、無理に聞き出すことを止めてくれた。
そういう些細な気遣いに心が温かくなって、本当に気持ちが軽くなっていく。
「うん」
そうだよ。
昔のことは、もう昔のこと。
今の私にはユーリがいるし、街の人たちだっていてくれる。
心配する必要なんてないんだ。
ガタゴン――
その時、扉が開く音が聞こえた。
ノックもなく、扉が動く音が。
街の人なら一度ノックをして声をかけてくる。
また子供が相談に来たのかな?
そう思って振り向いた。
予感がした――
根拠はなく、不意に感じた。
懐かしい感覚を。
「お久しぶりですね? お姉さま」
「……ラトラ?」