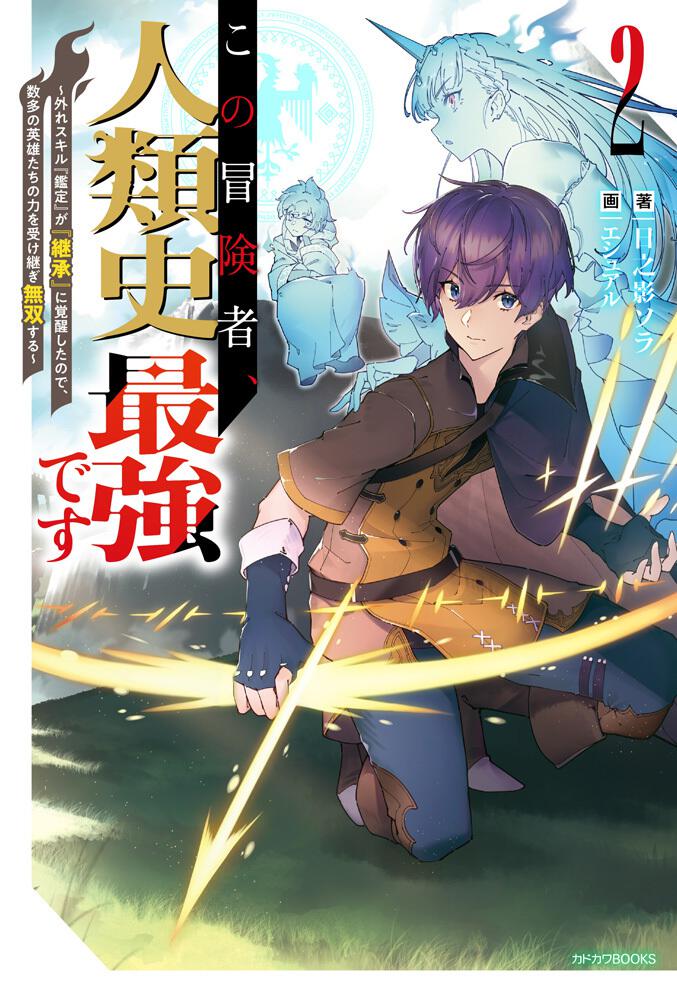13.春の祭り -前-
アトランタ周辺の地域は、四季という珍しい気候のめぐりがある。
私たちがこの街に来たのは、ちょうど寒い冬の終わり。
春の始まりを告げる強い風が吹き抜け、寒さを耐え抜いた動物や植物がひょっこり顔を出す頃だった。
「お祭り、ですか?」
「そう。春恒例のお祭りがあるんだよ」
春の温かさを実感し始めた頃。
それを教えてくれたのは冒険者のアリサさんだった。
アリサさんとは少し前、冒険者のお手伝いをしたときに知り合って、年齢は少し離れているけど女の子同士で話しやすくて。
気が付けばよく話したり、彼女のほうから教会へ遊びに来てくれるようになった。
この街に来て初めて出来たお友達だ。
「レナちゃんは、街の広場にある大きな木ってわかる?」
「あ、はい! 建物より大きくて立派な木ですよね」
アトランタの中心。
賑わう商店街を抜けた先にある広場には、見上げるほど背が高くて立派な木が生えている。
歴史がある木だからなのか、木の根の周囲は柵で囲われていて近づけないようになっていた。
「そうそう! あれはケラソスの木って言う名前で、世界中でたった一本しかない貴重な木なんだって」
「そ、そうなんですか?」
「らしいわよ。本当の所は知らないけど、かなり貴重なのは確か。その特徴が、春になるとピンク色の綺麗な花を咲かせるの」
アリサさんが言う春のお祭りの別名は『ケラソス祭り』。
春にだけ咲く綺麗な花を見ながら、一年の幸福や息災を願うという。
「健康とかだけじゃなくて、子供がほしいとか、出会いが欲しいなんてお願いする人もいるのよ」
「へぇ~ お願い事か……」
王都でもお祭りは珍しくなかったけど、祭りの中で願い事をしたりする習慣はなかった。
聖女という天に近い存在であることで、そういう精神的なお祈りをする意味があまりなかったからだ。
この街は歴史も古く、辺境で聖女が来たのも数十年ぶりらしい。
聖女が身近にいない街だからこそ、昔から残っている文化なのだろう。
「せっかくこの街に来たんだから、レナちゃんも参加したら? 露店とかも出て結構賑わうのよ?」
「露店ですか! 楽しそうですね~ でも、私なんかが行って邪魔にならないかな」
まだ一月ほどしか経っていない。
よそ者と言えばよそ者で、馴染めているかと言われれば曖昧だ。
街の人は優しいけど、少しだけ距離を感じることもある。
聖女だから一歩引かれているのかなと思って、何だか寂しい気持ちになった。
そんな風に考えて顔を伏せる私の不安を、アリサさんは一蹴する。
「そんなわけないでしょ。レナちゃんが来てくれたら、街のみんなも大喜びするわ」
「そ、そうですか?」
「ぜーったいそう。だから安心して参加しなさい」
と言って、アリサさんは視線を私の後ろに向ける。
「騎士君も一緒にね」
「え」
「えって何? まさか一人で行かせるつもりだったのかしら?」
「い、いやそんなつもりはないですよ。レナが行きたいなら、俺も護衛として参加しますから」
アリサさんに威圧されてタジタジのユーリ。
どうやらユーリは、年上の女の人が少し苦手らしい。
「護衛として、ねぇ~」
「な、何ですか?」
「別に何でもないわ。参加するつもりなら、どうして変な反応したのよ」
「あーいや、お祭りって人多いじゃないですか? 実は俺、そういう賑やかなのってどうも苦手で」
ユーリは頭に手を当てながらそう言った。
「そうだったの?」
「ああ。特に理由はないんだけど、何となく苦手というか」
初めて知った。
ユーリは初対面の人相手でも普段通りに話してるし、そんな風には見えなかったのに。
意外だ。
「でもそっか。ユーリが苦手なら私も止めておこうかな……」
「ほらもぉー、騎士君が余計なこと言うからよ!」
「え、えぇ……」
「賑やかなのが苦手って、そんなこと言って引き籠ってたらいつか身体からキノコが生えるわよ」
「うっ」
ユーリの身体からキノコが生える。
何となく想像して、少しおかしく笑いそうになった。
「そ、外には出てるじゃないですか。この間だってアリサさんたちの仕事手伝ったし」
「それはお仕事でしょ? 偶にはお仕事じゃなくて、遊びにも行きなさいって言ってるのよ! レナもだからね?」
「え、は、はい」
なぜか怒られているみたいだ。
私もユーリも、アリサさんの響く声に背筋がピンと伸ばされる。
「とにかく来なさい! お祭りは七日後だからね?」
「は、はい」
「騎士君も返事!」
「はい」
「よし! それじゃ私はお仕事に戻るから」
そう言って席を立ち、アリサさんは教会を出ていく。
私たちは外まで見送って、後姿が見えなくなるまで手を振った。
手を下ろした私が教会に戻ろうとすると、隣でユーリがぼそっと呟く。
「なぁレナ」
「どうしたの?」
「……あの人、何であんなに怒ってたんだ?」
「な、何でだろうね?」
私にもよくわからない。
だけどたぶん、私たちのことを心配してくれたのだと思う。
「お祭りは行かないとね」
「そうだな。これで行かなかったらもっと怒られそうだ」
「ふふっ、そうだね」
怒られたくないからなんてユーリは言うけど、私は少しワクワクしていた。